長野敬『わたしが選んだこの一冊』
『わたしが選んだこの一冊』
・2010年 『タイム・マシン』H.G.ウエルズ 著 宇野利泰 訳
・2011年 『虫を愛し、虫に愛された人』長谷川眞理子 偏
・2012年 『イカの心を探る』――知の世界に生きる海の霊長類 池田譲 著
・2013年 『カオスの紡ぐ夢の中で』金子邦彦 著
・2014年 『科学にすがるな!』宇宙と死をめぐる特別授業 佐藤文隆・艸場よしみ 著
・2015年 『ヒトはなぜ協力するのか』マイケル・トマセロ 著 橋彌和秀 訳
2010年度
『タイム・マシン』
H.G.ウエルズ 著 宇野利泰 訳
早川書房 [在庫なし 再版未定 古書で入手可]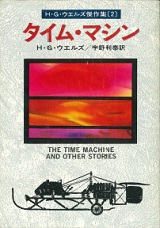 21世紀のいま、思想にも(進化論的な生命観)、科学技術にも(バイオ産業)、生物学的な生命理解が欠かせない。それ以前の1世紀半の土台の上に、この理解は築かれた。教科書に出てくるダーウィン、メンデル、パストゥール、コッホは全員19世紀に開拓的な仕事をした。H・G・ウエルズ(1866~1946)はそれより半世紀遅れて、社会に影響を及ぼした文筆の巨人だった。出世作の『タイム・マシン』(1895)は、第四次元である時間を移動し、80万年後の世界を体験して戻ってくる物語。すべてのSFの原点であり、生物学を学んだ背景も生かされているが、取り上げる理由はそれだけではない。
21世紀のいま、思想にも(進化論的な生命観)、科学技術にも(バイオ産業)、生物学的な生命理解が欠かせない。それ以前の1世紀半の土台の上に、この理解は築かれた。教科書に出てくるダーウィン、メンデル、パストゥール、コッホは全員19世紀に開拓的な仕事をした。H・G・ウエルズ(1866~1946)はそれより半世紀遅れて、社会に影響を及ぼした文筆の巨人だった。出世作の『タイム・マシン』(1895)は、第四次元である時間を移動し、80万年後の世界を体験して戻ってくる物語。すべてのSFの原点であり、生物学を学んだ背景も生かされているが、取り上げる理由はそれだけではない。
「リゾーム」という思考法がある。ものを見るのに、中心をなす命題からの整然とした枝分かれでなく、リゾーム(地下茎)のように横につなげていく。思想のしりとり遊びと言ってもいいのだが、人物の経歴をたどるときにも応用できる。ウエルズはアメリカのウィルソン大統領との討論、レーニン、スターリン、ルーズベルト大統領との会見、世界大戦(第一次)後の国際連盟の主唱など、社会活動でも目ざましかった。著述の大作では大戦の惨禍を動機とした『世界史大系』(1920)、生物学の普及を目指した『生命の科学』(1930、邦訳は昭和期に3回)がある。
『生命の科学』に絞って言えば彼は総監督で、執筆の中心人物はJ・S・ハクスリー(ウエルズが学生として学んだT・H・ハクスリー[ダーウィンの年下の盟友]の孫)だった。くだって2002年、線虫のゲノム研究でノーベル賞を得たシドニー・ブレナーは南アフリカの貧しい少年時代に図書館でこの本に出逢い、ぜひ欲しくて、紛失したと嘘の申告をし、罰金を払って手に入れたという。
『タイム・マシン』はSFの古典としてとにかく面白い。最初の出逢いはそれで結構。興味の起点から縦にも横にもリゾームをつなげていけば、知識も思想も目ざましくひろげられる。
読書案内。『タイム・マシン』はハヤカワ、創元SF、岩波、角川の各文庫が入手可能。ハヤカワ文庫の巻末の文章(荒俣宏)は、短いながら単なる解説的あとがきを超えた一篇。
【付記】ハヤカワは現在絶版かもしれないが、「日本の古本屋」の詳細検索(http://www.kosho.or.jp/public/book/detailsearch,do)でも応答はある。冊数が少なくても、売れればまたどこかから出品され、品切れにはならないだろう。
これに限らず今後の学習・研究でも、欲しい本・情報を手に入れる各種の工夫はある(定価より高いこともあるが、ときには文庫本をネット経由で「1円で」手に入れた経験もある)。
2011年度
『虫を愛し、虫に愛された人』
長谷川眞理子 偏
文一総合出版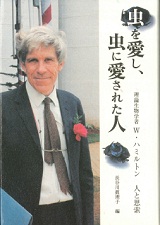 「虫を愛し…」というタイトルから、ファブルのような博物学者が運想されそうだ。ところがサブタイトルでは「理論生物学者」。いったいどうなってるんだ。そう、ウィリアム・ハミルトン博士(1936-2000)は、一生涯虫好きの「昆虫少年」であると同時に、「20世紀後半の進化生物学にもっとも大きな貢献」(編者序言)を果たした偉大な理論家でもあった。
「虫を愛し…」というタイトルから、ファブルのような博物学者が運想されそうだ。ところがサブタイトルでは「理論生物学者」。いったいどうなってるんだ。そう、ウィリアム・ハミルトン博士(1936-2000)は、一生涯虫好きの「昆虫少年」であると同時に、「20世紀後半の進化生物学にもっとも大きな貢献」(編者序言)を果たした偉大な理論家でもあった。
血縁選択(kinselection)とか包括適応度(inclusive fitness)などの語を、生物の授業で聞き知っている人もあるだろう。その代表的な論文は、1964年に専門誌『理論生物学雑誌(Journal of theoretical biology)』に発表された。アリやミツバチのワーカー(はたらき個虫)は、染色体の構成では雌だが不妊、つまり産卵しない。それなのにワーカーを生ずる遺伝形質は、女王が産む卵を通して代々伝わっていく。ダーウィンも頭を悩ませたこの矛盾に、彼は鮮やかな答えを提案した。
HIV(エイズウイルス)の起原にも、彼は取り組んだ。小児麻痺ワクチンに使われていたウイルスがアフリカでサルから人間に逆感染してHIVとなったという説があって、その証拠集めに現地コンゴに赴き、そこでマラリアに感染して急逝した。調査旅行のあと訪日も予定されていたので、日本の研究者は突然の悲報に愕然とし、その死を悼みつつ、記念に本書は編まれた。以前に『インセクタリウム』(上野動物園が発行していた広報誌で、いまは廃刊)に寄稿された、小編ながら魅力に富んだ自伝も再録されている。ブラジルで見た紫金色に輝くダイコクコガネ(動物の死骸を始末する甲虫)に思いを馳せて、死後はあの森に運んで貰いたい、美麗な葬儀虫が私を「埋葬」し、私は虫たちの子孫に姿を変え自然のなかで「虫に愛されて」生きていくという。幻想的なイメージ。
活動を振り返った自分の研究史(これは1993年の京都賞の受賞講演)や、交流の深かった日本の研究者による寄稿もあって、一生を通して博物学者であり、傑出した理論家であり、感性も豊かだった人柄(亡くなる直前に着手していた研究論集のタイトル、"Narrow roads of gene land"は芭蕉の「奥のほそ道」にちなんだという)を、いろんな角度から偲ぶことができ、誰でもたやすく読み通せる一冊だ。
付記。社会性昆虫を中心として展開された理論では、同じ巣の仲間は全員が遺伝子の共有度が高いから、自分では子を生まないワーカーもグループ全体の有利さに寄与する(包括適応度を高める)というのだが、この見方にも大きな限界があるという見直しの論文が、最近出ている(Nature466,1057〔2010])。もちろんハミルトンの大きな貢献がこれで減ずるわけではないが、科学はこうして「先人たちの肩の上に乗って」、次々にさらに遠くを見ていくのだ。
2012年度
『イカの心を探る』
――知の世界に生きる海の霊長類
池田譲 著
NHKブックス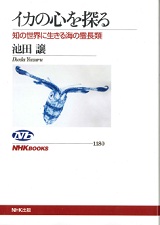 生物学をひと通りやってきた人は、副題をみて、おかしいと思うだろう。「知の世界に生きる海の霊長類」。分類学の開祖リンネが、人間とそれに似た一族をPrimates〔霊長類〕と名づけたのは、それらに共通の優位を見て取ったからだった(ただし彼は、サルや類人猿や人それぞれの起原は造物主による別個の作品という、十八世紀通りの常識に従っていた)。副題に言う「海の霊長類」は、深海探検で有名、そして潜水具アクアラングの開発者で替あるジャック=イヴ・クストーによる表現を借りたもので、海には伝説の人魚姫のほかには霊長類該当者はいないから、これは比喩であり、ただし比喩の主旨は、「知的」に特筆すべき存在というところにある。
生物学をひと通りやってきた人は、副題をみて、おかしいと思うだろう。「知の世界に生きる海の霊長類」。分類学の開祖リンネが、人間とそれに似た一族をPrimates〔霊長類〕と名づけたのは、それらに共通の優位を見て取ったからだった(ただし彼は、サルや類人猿や人それぞれの起原は造物主による別個の作品という、十八世紀通りの常識に従っていた)。副題に言う「海の霊長類」は、深海探検で有名、そして潜水具アクアラングの開発者で替あるジャック=イヴ・クストーによる表現を借りたもので、海には伝説の人魚姫のほかには霊長類該当者はいないから、これは比喩であり、ただし比喩の主旨は、「知的」に特筆すべき存在というところにある。
イカが知的と言われると、虚を衝かれた感じがするだろう。彼らと同じ軟体動物には二枚貝とか水中の巻き貝、陸のカタツムリ、さらに貝殻のないナメクジやウミウシも属しているが、どれもあまり冴えた存在には見えない。そこにあって、われわれと同じ原理によるカメラ眼をもち、敏捷に行動するイカとタコの「知性」がひときわ目立つことは、間違いない。全身デザインが違うのでイメージしにくいが、全身の中央に陣取る中枢神経系(脳)は無脊椎動物では随一の立派なものだ。
イカと神経といえば、生物学のふた通り目をやった人ならすぐ連想するのは、ポジキンとA・F・バクスレーがヤリイカを材料として神経の刺激伝達の分子メカニズムを研究してノーベル賞(1963年)を得たことだ。ただしこれは、中央部分に位置する脳から、イカのトレードマークである前端の三角形(外套)の裏に隠れた噴水孔まで刺激信号の急送用に特に発達した神経の枝(軸索)の太さを利用したもので、本書の主題と直接につながるわけではない。では主題は、具体的にはどのような立場で展開ざれているのか。
ペットのイヌとか小鳥とかに関しては、われわれは同じ陸の動物として相手に「心」を想像しやすい。「海の霊長類」であるイカ、またタコについても(パウル君のサッカーW杯の予言は座興だったが)、想定は難しくても、同じように応の世界」にもとつく理解が可能どころか啓発的でもあることを、著者は熱心に説いている。祉会生物学、小鳥の歌(シーズンごとの脳の一部分の更新や、歌の「方言」の存在)、サル学の成果、さらにマキャベリの「君主論』や「赤ちゃん・子育て学」まで、思いがけない言及が次々に繰り出される。著者のような見方はまだひろく受け入れられたものではないので、心理学・行動学・社会生物学などどの分野でも、それぞれの基本にまず立ち戻った上で、そこからイカやタコを改めて理解することが必要という立場を、著者は取っている。だから本書からは、「海の霊長類」を理解しようという意欲と、分子レベルよりは行動レベルで近年展開されほぼ確立してきた生物学の諸分野を入門的な原理からたどりなおすという、二重の新鮮な刺激を受け取ることができる。
2013年度
『カオスの紡ぐ夢の中で』
金子邦彦 著
ハヤカワ文庫 表紙の絵は、なにか蝶の標本のようにも見える。表題に「夢の中で」とも言う。夢で胡蝶と化した中国のはるか昔の思想家、荘子(正しくは本人は荘周で、その発言録が『荘子』)と関係があるのか?しかしこの本は「〈数理を愉しむ〉シリーズ」という新書の一冊である。どうも波長が合わない。
表紙の絵は、なにか蝶の標本のようにも見える。表題に「夢の中で」とも言う。夢で胡蝶と化した中国のはるか昔の思想家、荘子(正しくは本人は荘周で、その発言録が『荘子』)と関係があるのか?しかしこの本は「〈数理を愉しむ〉シリーズ」という新書の一冊である。どうも波長が合わない。
科学理論のほうで複雑系というのが一時期もてはやされた。ニュートンの方程式につながるような現象は、難解に見えても結局は複雑な単純系であり(言葉の矛盾だが)、その反面それと本質的に違うもの、たとえば生物の発生の仕組みなどには別の原理が必要だと見るのが、複雑系という立場だ。ところがやはり生物らしい他の現象である遺伝が、A・G・C・Tの符号の順列組合わせという物理学的な理屈(受験生なら誰でもお馴染みの遺伝暗号)で記述できたことから、生物学も結局は物理学に帰着するのではという意見も出て、そうした議論のなかで複雑系という言葉が目立つようになった。ただし「複雑」という言葉は便利すぎて、生命現象などが「やはり生物は複雑だから」という言い方で片付けらることも多く、こうした安易さも一因となって、複雑系が万能思想でないことも反省された。いまコンピュータの性能が複雑さに正面から取り組むほどに向上し、また複雑系という語の流行りすぎの熱もさめた時期にあって、この発想を見直すことも、大いに有意義だろう。
この本は15年ほど前の文庫本の再刊で、収録されたエッセイは1996年から97年にかけて当時の科学雑誌への連載だが、いま読んでも示唆に富む。後半の「小説 進物史観」は、コンピュータの研究チームによる物語の自動生成プログラムの開発を、愉快なパロディとして描いた作品。どんな結末になるかは、読んでのお楽しみ。
じつはこの小説は、本書の今度の刊行でも、ふう変わりな役目を果たした。研究チームは生成した物語を、もっともらしい架空の著者の名前で次々に世に問うというのが小説の筋書きで、架空名の一つに円城塔李久というのもあった。ところが実際に、これをペンネームとする異色の著者が世に出て(なんと理論物理学の出身。もの書きに転進する以前に、本書の著者である金子邦彦の研究室に所属していた〉、この円城塔は平成24年に芥川賞を得た。受賞作品の表題は『道化師の蝶』。そこで、生成プログラムとして円城塔李久の名前も出てくるお話も含む本書が今回再刊されるにあたって、作家の円城塔は、巻末に解説を書いている。そのことと、本書の表紙デザインの「蝶」みたいな姿と、そしてこんな図形を描き出す複雑系の「カオス」という特性は、たがいに複雑微妙な関連がある―といっても、何やら雲をつかむように聞こえるが、興味のある人はまず本書を手にとって見てください。
これからの現実(リアル)世界の理解には、コンピュータが描き出すヴァーチャルな世界の理解も、ますます大きな比重を占めるようになってくるだろう。
2014年度
『科学にすがるな!』宇宙と死をめぐる特別授業
佐藤文隆・艸場よしみ 著
岩波書店  ヴェテランの女性編集者(艸場よしみ)が、身のまわりで起きた友人の死や、自分もがんの疑いなどで不安に駆られ、科学に気持のよりどころを得られないかと、科学者にメールを送った。受信した相手は代表的な理論物理学者で、前世紀の後期に素粒子研究が盛り上がったころに業績をあげ、紫綬褒章も受けている著名人(佐藤文隆)。このきっかけから始まった独特な調子の対談が、取材者側の見方が変わってゆく「特別授業」へと育ち、本にまとまった。
ヴェテランの女性編集者(艸場よしみ)が、身のまわりで起きた友人の死や、自分もがんの疑いなどで不安に駆られ、科学に気持のよりどころを得られないかと、科学者にメールを送った。受信した相手は代表的な理論物理学者で、前世紀の後期に素粒子研究が盛り上がったころに業績をあげ、紫綬褒章も受けている著名人(佐藤文隆)。このきっかけから始まった独特な調子の対談が、取材者側の見方が変わってゆく「特別授業」へと育ち、本にまとまった。
最初の対談のとき、宗教や哲学からでなく科学の立場で死を見る見方を艸場が問いかけたのに対して、理論物理学者はこう答える。「ここにヘビがやってきたとしよう。単にそれは、ヘビをつくっている分子が集団的に移動したにすぎない。」そういう見方で見たとき、漠然ともっていた見方がひっくりかえるだろうかというのが、あなた(艸場)の興味のあるところだと思う、と物理学者は指摘し、続けて、「だがね、自然や自然物がサイエンスで解明されると思うのは間違いである。」
今どきの科学者として、これは珍しくもない見方だ。たとえばこの本の紹介者(長野)は生物学の出身だが、まさにぴったりの比喩と感じた。だがその反面、そう理解したからといって、死の不安が消えたりしないことも当然だろう。
ただ、死生観を問う相手として素粒子研究の理論物理学者を選んだのは、質問者として照準の合わせ損ないだったように見える。もし常識的に生物学者とか医学者を相談相手に選んでいたらどうか。「生物と無生物はやっぱり違うからね」とか、細胞一個も「生命をもっている」とか、じつは何の答にもならない言い方で無難に、しかし陳腐に終わったかもしれない。今回は照準の合わせ損ないのおかげで、手ごたえのある議論(あるいは取材)が続くことになった。遺伝子が生体の設計図だという、ありふれた位置づけもここには出てこない。それを突き抜けて、「遺伝子であろうが何だろうが、すべて分子の組み合わせでつながっている」と佐藤は言う。(ただしこれは生物学で言う素朴な還元主義ではない。「生物はクオークとレプトンの系である」という壮大な宣言はその通りでも何かが欠落しているという自覚を、佐藤はすでに自分でも論じていた。)
世界のとらえ方として、身体の外側にあるすべての実在(第一の世界、「外界」)と、たとえばコップを手にもったとき、その手ごたえや色合いから、コップがそこに、外部にあると感じ取る第二の実在(「内界」)があり、さらに、こういう理解を社会が共有し受け継いでゆく仕方(「第三の実在」〉があると、佐藤は言う。「人間は社会的な動物だ、言語とか慣習とかは全部第三の実在である、文学も科学も宗教も。」これは哲学者カール・ポッパーが言う難解な「世界三」とは違うが、世界三が世間に向かって開かれ、科学自体によって手直しされ、緻密になり、普及してゆく姿と位置づけられるかもしれない。こうした基本の考え方は最初の対話(第一回の取材)ですでに提示され、それらが回を重ねるなかで、展開されてゆく。
「死」をどのように受け取るかという、本書のきっかけとなった主題も、最初からすでに提示されているわけだが、第一回のヘビのたとえ話の外形はそのままでも、特別授業の受講者(艸場)の受け取り方は変わってくる。授業の同席者(本書の読者)にもこの筋道はわかりやすく案内されているが、各人それぞれが自分なりの違う意見も、もつことができるだろう。
2015年度
『ヒトはなぜ協力するのか』
マイケル・トマセロ 著 橋彌和秀 訳
勁草書房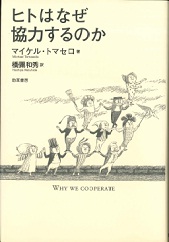 本書の表題にあり、中心主題でもある「協力」という言葉には個人的に拒否反応があった。今年は敗戦後70年で、さまざまに回顧が語られるつど、戦争に否応なく協力させられた悲惨な結末を思い出させられる。都市大空襲、戦艦武蔵の撃沈、沖縄の歴史と現状。拒否は一部、体質に組み込まれている。今回の震災のあとでも「絆」とか聞くと、やつ当たりとわかっていても、わずらわしさを感じてテレビのスイッチを切ったりする。
本書の表題にあり、中心主題でもある「協力」という言葉には個人的に拒否反応があった。今年は敗戦後70年で、さまざまに回顧が語られるつど、戦争に否応なく協力させられた悲惨な結末を思い出させられる。都市大空襲、戦艦武蔵の撃沈、沖縄の歴史と現状。拒否は一部、体質に組み込まれている。今回の震災のあとでも「絆」とか聞くと、やつ当たりとわかっていても、わずらわしさを感じてテレビのスイッチを切ったりする。
もう一つべつの回路からの反応は、生物学での進化・遺伝子観から来ている。ドーキンスの『利己的遺伝子』には動物の協力、利他性をからかって、「ぼくの背中を掻いておくれ。お返しにお前を踏んづけてやろう」とかいう調子の一章があった。彼の言い分はかなり極端で、そのまま鵜呑みはできないが、生物学の学習期間に受けた洗脳の影響は残り、いまも生物問の関係を見るときの基調だ。ダーウィンはミツバチの「相互協力」などの難問に戸惑ったが、進化の理論観も今では、個々の遺伝子の勝手な発現だけでなく、システムとしての遺伝子群、さらにゲノムの「協力」も視野に入れるようになってきた。それでも、根源にさかのぼる議論にはどうも手が出しにくかった。それなのに今回の選球はなぜか。
まず協力といっても、多細胞生物成立以来などという大上段に構えた問題設定ではない。ヒトと仮名で書いてあるが時折の動物界への言及以外に土俵はあまり拡大されず、「幼いヒトの子どもおよび最も近縁な霊長類」が対象なので議論はまとまりが良い。そして他者と協力する(利他性)といっても、生まれつき全部備わっているとか、全部誕生後に植え付けられるのでなく、生来の性向が文化環境・言語環境によって育てられてゆく。
いかにもありきたりの話に聞こえるが、有名なタナー講義での招待講演を整理したもので、4人の討論者も招いて手応えある議論を展開している。4人はそれぞれの立場から批判の見解も述べているが、トマセロは批判者の主張をも、巧みに自分の筋書きに組み込んでしまう。たとえば利他性が霊長類の祖先以来持ち越された先天的なものという考えと、誕生後に社会的な生活環境のなかで育ってゆくという主張について(トマセロ自身は社会的な環境として特に言語などのコミュニケーションが重要と位置づけているのではあるが)、4人の論者のうち2人の名前を借りて、もちろんどちらも大事だが、時間的なずれがあり、特に生後1年間は「前半スペルギ説、後半デック説」と整理する。また協力的な利他行動が進化の道筋に沿って進んできたことについても、狭い血縁内での行為と、作戦的な分担で大きな獲物を仕留める協調行動のどちらを重く見るかについて、他の2人の言い分を借りれば「類人猿の行動ではシルク仮説、ヒト段階でスキームズ仮説」ということで、進化の道筋が理解できる。
簡潔にまとめられた講演と4名のコメントを読んで、読者は自分ならば問題をどう展開できるだろうかなど、考えをすすめることができる。また、時代をさかのぼって、本書の出発点である霊長類以前の動物の世界全体では、ホッブズの言う万人と万人の闘争の状態だったのだろうかと改めて見直す必要も見えてくる。