谷川道雄『わたしが選んだこの一冊』
『わたしが選んだこの一冊』
・2010年 『代表的日本人』内村鑑三 著 (鈴木範久訳)
・2011年 『アイヌの物語世界』中川裕 著
・2012年 『後世への最大遺物 デンマルク国の話』内村鑑三 著
・2013年 『イエスの生涯』遠藤周作 著
2010年度
『代表的日本人』
内村鑑三 著 (鈴木範久訳)
岩波書店  本書は内村鑑三(1861~1930)が1908年(明治41年)に書いたRepresentative Men of Japanの日本語訳である。内村はクラーク先生の「少年よ大志を抱け」で有名な札幌農学校の出身で、在学中に洗礼を受けてキリスト教徒となり、明治の思想界で大いに活躍した。彼が日露戦争で非戦論を唱えたことはよく知られている。戦争に正義の戦争などはなく、すべて悪だというのが、彼の主張であった。学校教員時代、教育勅語の奉読の時敬礼をしなかったというので、不敬事件とされ(今の日の丸・君が代事件とよく似ている)、職を追われて貧窮の生活をよぎなくされた。本書はその時期に書かれたものである。
本書は内村鑑三(1861~1930)が1908年(明治41年)に書いたRepresentative Men of Japanの日本語訳である。内村はクラーク先生の「少年よ大志を抱け」で有名な札幌農学校の出身で、在学中に洗礼を受けてキリスト教徒となり、明治の思想界で大いに活躍した。彼が日露戦争で非戦論を唱えたことはよく知られている。戦争に正義の戦争などはなく、すべて悪だというのが、彼の主張であった。学校教員時代、教育勅語の奉読の時敬礼をしなかったというので、不敬事件とされ(今の日の丸・君が代事件とよく似ている)、職を追われて貧窮の生活をよぎなくされた。本書はその時期に書かれたものである。
本書が英語で書かれたのは、キリスト教国でない日本にも、世俗のキリスト教徒などはるかに及ばない、キリスト教的精神をもった人物が存在したことを、世界の人びとに知らしめるためであったという。彼のいうキリスト教的精神とは何か。それはイエス・キリストを信仰し、聖書を読み、教会へ出かけて牧師の説教を聞き、祭壇を礼拝することではない。財産や地位や名声などを省みず、つまり自分一身の利益を捨て、人びとの為に献身的に働いて一生を送った、その純粋な人間の魂のことである。
彼がその代表例として挙げたのが、西郷隆盛、上杉鷹山、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮の5人である。この5人は時代もちがい、やったこともちがう。しかし人びとのしあわせのためにその人生を捧げたことは共通している。そのことで迫害を受け、文字通り死を賭して戦った人たちでもある。さらに共通しているのは、その私生活で、勤勉、節約につとめ、いわゆる清貧に甘んじた点である。
彼らは努力してそうしたのでない。自分の精神が自ずとそこに向かったのである。彼らをそこにみちびいたものは、天の道にしたがう(日蓮の場合は仏の真の教え)という、次元の高い内心の声であった。
この5人の事蹟について、ちがった面からの批判もいろいろとあり得る。内村はそれを承知の上でその純粋な魂を取り出したのだ。とてもそんな人間にはなれそうもないという人が多いであろう。しかし日本の過去にこうした人物が現れ、その徳を慕って何万、何十万、いや無数の人びと、がそのあとに続いて日本の社会を作って来たことは、心にとどめておいてほしいとおもう。
2011年度
『アイヌの物語世界』
中川裕 著
平凡社(平凡社ライブラリー)  私たち人間は、山や川や動物や植物などのいわゆる自然に囲まれている。自然は人間にとって生活環境であり生存条件である。しかし人間の文明生活はかえって、自己の生活環境を破壊し、人類の生存を危うくするところまで来てしまった。その反省から、自然との共生といった言葉がしきりに使われるようになっている。
私たち人間は、山や川や動物や植物などのいわゆる自然に囲まれている。自然は人間にとって生活環境であり生存条件である。しかし人間の文明生活はかえって、自己の生活環境を破壊し、人類の生存を危うくするところまで来てしまった。その反省から、自然との共生といった言葉がしきりに使われるようになっている。
しかし、共生という以上は、相手に主体がなければならない。鳥や昆虫や草木それぞれの主体を私たちは実感することができるだろうか。実感できるようにみえても、せいぜい鑑賞したり、ペットとして愛玩するにすぎないのではなかろうか。自然は近代の人間にとって単なる客体でしかないのではないか。「ひと」と「もの」という場合、自然は結局「もの」の範疇を出ることができなかったのではなかろうか。とすれば「ひと」は「もの」とどうやって共生関係を作ることができるだろうか。
ところが、これと全く異なる自然観をもつ人びとがある。日本列島北辺に住んできたアイヌの人たちである。かれらは、人間(アイヌとは人間の意)の世界の他に、もう一つの世界があると考えている。人間を除く自然界のすべてのものは、みな「カムイ」とよばれる。「カムイ」とは「人間にない力」をもったものという意味で、たとえば何キロも川をさかのぼる鮭は、人間にない泳ぐ力をもっているし、熊は人間のもたぬ毛皮を作り出す。それらの個体の一つ一つが「カムイ」(総称すれば鮭カムイ、熊カムイ)なのである。人間はそれらの一部を肉として食べ、毛皮を衣料とするが、それは「カムイ」側からの人間への贈物である。抽象的な自然の恵みなどではない。人間の方でも、かれらの喜ぶ酒や御幣(木を削って作る)を捧げてかれらに感謝する。
つまり「人間の世界」(アイヌモシリ)と並存してもう一つの世界「カムイの世界」(カムイモシリ)があって、この両世界は対等の関係にあり、かつ互いにパートナーの役を果たしているというのである。これこそまさに[自然との共生」の世界である。
詳しいことは、この『アイヌの物語世界』を読んでほしい。著者の中川裕氏は東大出身の言語学者で現在千葉大学に勤務するが、アイヌ語の現地調査を続けているうちに、アイヌの世界の魅力にとりつかれ、アイヌの語り部たちとの厚い信頼関係のもとで、彼女らの口調する神謡、説話、英雄叙事詩などを採集してきた。いま亡びつつあるアイヌ語とアイヌ文化、そしてそれを伝える人びとが、年老いて少なくなりつつある現状を考えると、貴重な仕事である。
私はあるとき著者に向って、「あなたはカムイの世界を信じますか」とぶしつけな質問をしてみたところ、「アイヌの語り部たちの場に入ると、自分もそういう気持ちになる」との答えだった。アイヌの人びとから見れば、和人(アイヌ以外の日本列島人)の自然観は単調で索漠としたものに映るにちがいない。しかし和人にもかつては「カムイの世界」があり、歴史の中で消えてしまったのではなかろうか。
2012年度
『後世への最大遺物 デンマルク国の話』
内村鑑三 著
岩波文庫  人は誰でも自分の人生を有意義に送りたいとおもう。そしてその自分を他の人びとにも認めてもらいたいとおもう。意義ある人生を送るなどという気持ちはもうとっくに失くしてしまったという人でも、どこか心の底にはそういう気持があり、それを何かの原因であきらめてしまって日々の人生を送っているのではないか。しかし今の世の中はひどい就職難。たとい就職できたとしても生きてゆくのにせい一ぱいで、有意義な人生などどこの国の話かとおも謡だが、そのようにしてかけがえのない自分の生涯が日一日と消費されてゆくことを、私たちはただあきらめるしかないのだろうか。その中でどう考えたらよいのだろうか。
人は誰でも自分の人生を有意義に送りたいとおもう。そしてその自分を他の人びとにも認めてもらいたいとおもう。意義ある人生を送るなどという気持ちはもうとっくに失くしてしまったという人でも、どこか心の底にはそういう気持があり、それを何かの原因であきらめてしまって日々の人生を送っているのではないか。しかし今の世の中はひどい就職難。たとい就職できたとしても生きてゆくのにせい一ぱいで、有意義な人生などどこの国の話かとおも謡だが、そのようにしてかけがえのない自分の生涯が日一日と消費されてゆくことを、私たちはただあきらめるしかないのだろうか。その中でどう考えたらよいのだろうか。
内村鑑三の『後世への最大遺物』は、そうした問いへの完全な処方箋ではないが、何か考えさせてくれる文章である。これは内村が1894年(明治27年)に軽井沢の夏期学校でクリスチャンを対象に行った講演である。内村自身がクリスチャンだが、彼は教団の偽善的な傾向をきらってどこの教会にも属さず、ただキリスト教の人道的精神に立って行動・発言し、明治の思想界に大きな影響を与えた。その日露戦争反対運動はよく知られている。この講演の中にもキリスト教の話がしぼしば出てくるが、それは読みとぼしても構わない。彼の訴えるところは、人間がいかなる生涯を送るべきかということである。
内村はいう、人はだれでも社会に大きな貢献をして自分の名を後世に残したいとおもう。例えぼ財産を作って病院や学校を建てる。それは大いに結構なことだが、財産が作れなかったらどうするか。何か事業を思いついてそれを成功させる。事業の才能がなかったら?文筆で社会に影響を与える。では文才もなかったら、と問いつめて行って、では何の能力もない普通の人間は何も貢献できないのかという根本間題に迫る。それに対する彼の答えはこうである。
「後世の人がわれわれについてこの人たちは力もなかった、富もなかった、学問もなかった人であったけれども、己の一生涯をめいめい持っておった主義のために送ってくれたといわれたいではありませんか。これは誰にも遺すことのできる生涯ではないかと思います」。
ここで「主義」と言っているのは、「信念」と読みかえてもよいだろう。何の特別な能力もない平凡な人間が、自分の信ずる道をひたすらに歩み、その精神が他人にも伝わってゆく、これこそ「後世への最大遺物」だと説くのである。
それでは、どうやったら自分の信念を持つことができるかが次の問題だが、内村はそこまでは言及していない。キリスト教徒たちにそれを言う必要はなかったのだろうが、信仰を持たない者はやはり自分で考えてゆくしかない。大学生活の中心的課題は、自分のあるべき人生について何かをつかむことだとおもうが、どうだろうか。本書付載の「デンマルク国の話」も、併せて一読をすすめたい。
2013年度
『イエスの生涯』
遠藤周作 著
新潮文庫
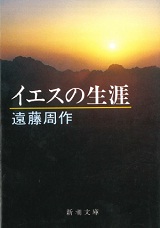 中学三年の男子が、いじめに苦しんで、今日もひとり自らの命を絶ったようだ。この学校では校長先生が全校生徒を集めて、「いのちの大切さ」について訓話を行なうことだろう。しかし、「いのちの大切さ」をいくら説いても、いじめで追いつめられている者にとっては、何の効果もない。この苦しみから一日も早く逃れたいと思うだけだ。
中学三年の男子が、いじめに苦しんで、今日もひとり自らの命を絶ったようだ。この学校では校長先生が全校生徒を集めて、「いのちの大切さ」について訓話を行なうことだろう。しかし、「いのちの大切さ」をいくら説いても、いじめで追いつめられている者にとっては、何の効果もない。この苦しみから一日も早く逃れたいと思うだけだ。
いじめにどう対処するか、はてはいじめとは何か、といった議論が教育界や識者の間でさかんに行なわれている。それも必要なことではあるが、それが苦しみ悩んでいる児童や生徒の心に届くわけではない。彼等、彼女等にとって、欲しいのは、自分の苦しみを自分と一緒に苦しみ、一緒に泣いてくれる人ではないか。そんな人がもしもいてくれたら、こうした痛ましい選択は、少しは避けられるものではなかろうか。
そんな人がこの世の中にいるのだろうか。自分を可愛がってくれている人でも、所詮は、私の苦しみ、みじめさを分かちあってくれず、ただ傍から心配してくれるだけだ。
しかし、本書の著者遠藤周作(1923年~96年)は、人の苦しみを自分の苦しみとし、自分のみじめさを自分と共に泣いてくれる人が、この世に実在した、それがイエスだというのである。イエス・キリストと言えば、人びとは、神の子であり、人間を救済するためこの世に遣わされて数々の奇蹟を行なった人だと考えるだろう。しかし遠藤はこうした観念を全く捨ててしまって、「共に泣く人イエス」という一貫したイメージでこの伝記を書いた。
「イエスがこれら不幸な人々にみつけた最大の不幸は彼等を愛する者がいないことだった。彼等の不幸の中核には愛してもらえぬ惨めな孤独感と絶望とが何時もどす黒く巣くっていた。必要なのは『愛』であって、病気を治す『奇蹟』ではなかった。人間は永遠の同伴者を必要としていることをイエスは知っておられた。自分の悲しみや苦しみをわかち合い、共に泪をながしてくれる母のような同伴者を必要としている」。
イエスが悲しみや苦しみを分ちあい、共に泣こうとしたのは、自分を正しいと思っている人、生活に満足している者、金のある人などではなく、ハンセン病のような不治の病人、不具者、身よりのない老人、身体を売って生きなければならない女たちなど、世の中からさげすまれ、見捨てられた人たちである。そうした人たちと共に泣き苦しむそういう人間が、この世界にたしかに一人はいる。この事実を証明するために、イエスはひたすら「愛」を説き、既成のユダヤ教から排斥され、ローマ帝国の支配の下で十字架を背負って死んだのである。
遠藤が描いたのはこうしたイエス像であって、神の子として霊能を授けられた救世主の姿ではない。キリスト教徒ではない私に、ここの見方が事実として正しいかどうかは分らない。しかし敬虔なカトリック信者である著者が、事実としてのイエスよりも真実としてのイエスを描くことに全力を傾けたこの書は、私たちにとってもこよなき救いの書である。世界各国で翻訳され、国際文学賞やさまざまな賞を受賞し、ひろく世界の人びとに読まれてきたのも、そのためであろう。