木村 敏『わたしが選んだこの一冊』
木村 敏
『わたしが選んだこの一冊』
・2011年 『生物の世界』今西錦司 著 講談社(講談社文庫)
・2012年 『善の研究』西田幾多郎 著 岩波文庫
・2013年 『風土』――人間学的考察―― 和辻哲郎 著 岩波文庫
・2014年 『省察』デカルト (三木清訳) 岩波文庫 (山田弘明訳) ちくま学芸文庫
・2015年 『西田幾多郎』〈絶対無〉とは何か 永井均 著 NHK出版
・2020年 『ゲシュタルトクライス―知覚と運動の人間学』
ヴィクトーア・フォン・ヴァイツゼカー著木村敏・濱中淑彦訳 みすず書房
2011年度
『生物の世界』
今西錦司 著
講談社(講談社文庫)
 「この小著を、私は科学論文あるいは科学書のつもりで書いたのではない。それはそこから私の科学論文が生まれ出ずるべき源泉であり、その意味でそれは私自身であり、私の自画像である。」
「この小著を、私は科学論文あるいは科学書のつもりで書いたのではない。それはそこから私の科学論文が生まれ出ずるべき源泉であり、その意味でそれは私自身であり、私の自画像である。」
これは1941年、太平洋戦争開戦の年に出版された本書の冒頭の文章である。このすぐ後に著者はこうも書いている。「今度の事変[日中戦争]がはじまって 以来、私にはいつ何時国のために命を捧げるべきときが来ないとも限らなかった。……私の命がもしこれまでのものだとしたら、私はせめてこの国の一隅に、こ んな生物学者も存在していたということを、なにかの形で残じたいと願った。……この目的に適うものとしては、自画像をかき残すより他にはあるまいと思っ た。」
つまり本書は、定説となっているダーウィン進化論を否定して、独自の「今西進化論」を世に問うた著者が、39歳の若さで書いた「自画像」であると同 時に「遺書」だったのである。
動物でも植物でも、生物は一匹一匹の「個体」として生きている。一方で生物は、他の種類とは構造や生態 が違うそれぞれの「種」としても生きている。種が生き続けて行くためには、それに所属する個体が繁殖して世代をつないで行かなければならない。こうして生物は、個体としても種としても生命活動を営みながら生きて行く。
生きて行くことができるためには、生物は環境に対して主体的に行動しなけれぼならない(本書69~71頁)。今西がこの本を執筆していた当時、彼が深く影響を受けた西田幾多郎を中心とする京都学派の哲学では、「主体性」をめぐる議論がしきりに行われていた。
よく知られているように、ダーウィンの進化論は環境への適応能力に勝る個体が適応性の劣った個体を打ち負かすことによって自然淘汰(選択)が行われ勝ち 残った個体が子孫を繁殖することによって結果的に種が進化して行くという原理を主張しているが、今西はこの自然淘汰の原理を認めない。「自然淘汰説というものは生物の環境に対する働きかけというものを全然認めないで、環境の生物に対する働きかけだけを取り上げている」(150頁)。「生物が生きるということは身体を通した環境の主体化であり、それは逆に身体を通した主体の環境化である」(152頁)のに、ダーウィンは「環境の主体化を考えないで、主体の環境化のみを考えようとした」(155頁)。
ダーウィンの進化論は個体の適応能力め優劣のみを問題にするが、その優劣は自然選択という環境からの圧力に対抗する、個体の機械的で受動的な抵抗力の差にすぎない、生物と環境は、生命の座である身体を通じて主体的に結ばれている。生きて行くという営みの根本にある主体性、「生物が生物としてこの世界に現れたはじめから生物に具わった性格」(71頁)としての主体性を重視する今西のこの認識は、 受験生諸君にとっても大きな心の支えとなるものだろう。
2012年度
『善の研究』
西田幾多郎 著
岩波文庫  受験生の諸君にこの本を推薦するにっいては、実は非常に迷った。とにかく難解この上ない。よほどの才能の持ち主でなければ、読み進めることはできないだろう。これを書いている私自身も旧制高校時代にこの本をもってはいたが、もちろん理解できなかった。
受験生の諸君にこの本を推薦するにっいては、実は非常に迷った。とにかく難解この上ない。よほどの才能の持ち主でなければ、読み進めることはできないだろう。これを書いている私自身も旧制高校時代にこの本をもってはいたが、もちろん理解できなかった。
しかし、ある本を手許にもっているということ、理解できるできないにかかわらずそれを読む作業を自分に課しているということ、自分はこの本を読んでいると いう意識、いってみればその自覚を大事にするということ、それに値する本がもしあるとするならば、この本は間違いなくそんな本の一冊であるだろう。
わからなくてもいいのだ。八十歳を超えて、人生の大半を西田哲学とのつきあいで過ごしてきた私だが、この本に書いてあることが本当に理解できているとは到 底いえない。西田幾多郎自身でも、この本に書いたことに納得できず――ということは自分で書いたことが自分にとっても理解できずーー、そこから次々に書き 方を変え、考え方を変えて、あの壮大な西田哲学の世界を展開していったのだから。しかし、これはどんな思想家についても言えることだけれども、その処女作 には彼の全生涯にわたる思想が萌芽のかたちで必ず含まれている。この本を一冊もっているということは、二十数巻の西田幾多郎全集をもっているというのと、 重さの上ではそんなに違わないとすら言える。これが私の、迷いに迷ったあげく、受験生諸君にこの本をお薦めしようと決めた理由である。この私の気持ちは、 わかっていただけるだろうか。
この本を開けてみると、まず「序」が書かれている。執筆の事惰、全体の構成などを述べたあとで、次のページにこんなことが書いてある。「純粋経験を唯一の実在としてすべてを説明して見たいというのは、余が大分前から有っていた考であった。〔中略〕個人あって 経験あるにあらず経験あって個人あるのである、個人的区別より経験が根本的である〔後略〕」。――劇作家の倉田百三が感涙にむせんだという有名な文章なのだが、これが理解できれば、西田哲学の根本は理解できたということになる。
ふつうに「経験」というと「なにかを経験する」ということで、それには内容があるのだが、まったく無内容で、ただ「経験している」という「こと」だけの経験を、「純粋経験」と考える。無内容だから漠然としている けれども、意識はあるのだから周囲とのつながりは保たれている。この「周囲とのつながり」には私という個人のその場での事情はまったく反映されていない。 むしろこの「つながり」があるからこそ私が私として意識されるのだ。そういうことをこの文章は語っている。
おわかりだろうか。わからなくてもいい。こんな話がこの本に書いてある、そのことだけを承知して、そしてこの本を大事にもっていてほしい。いつか必ずなにかの役に立つだろう。
2013年度
『風土』――人間学的考察――
和辻哲郎 著
岩波文庫 この本には特別な思い入れがある。私が1961年から63年まで、最初の留学先としてドイツのミュンヘン大学精神科へ出かけたとき、研究テーマとして選んだのは「日独両国の鬱病についての比較研究」だった。最近非常に増えている若い人たちの「現代型響病」とはまったく違って、本格的な鬱病(メランコリー) の主要症状の一つは「罪責体験」、つまり罪の意識である。罪の意識といえば当然ながら宗教と深い関係がある。カトリック色の非常に強いミュンヘンの患者 と、特定の宗教を信仰しない京都の患者ではかなり差があるのではないかというのが最初の予想だった。
この本には特別な思い入れがある。私が1961年から63年まで、最初の留学先としてドイツのミュンヘン大学精神科へ出かけたとき、研究テーマとして選んだのは「日独両国の鬱病についての比較研究」だった。最近非常に増えている若い人たちの「現代型響病」とはまったく違って、本格的な鬱病(メランコリー) の主要症状の一つは「罪責体験」、つまり罪の意識である。罪の意識といえば当然ながら宗教と深い関係がある。カトリック色の非常に強いミュンヘンの患者 と、特定の宗教を信仰しない京都の患者ではかなり差があるのではないかというのが最初の予想だった。
ところが実際に調べてみると、罪責体験の出現頻度にはほとんど差が出なかった。唯一見られた大きな違いは、ドイツ人の患者の多くが自分の罪を神の教えや道 徳に対する違反として個人的に受けとめるのに対して、日本人の患者はそれを家族や職場の人たちに迷惑をかけているというかたちで、他人との関係に対する罪 として感じやすいという点だった。
私はこの違いを、ヨーロッパ人と日本人がそれぞれ何千年かにわたってそこで生き、そこで生活してきた「自然」の違いということで理解してみようと思った。そのとき非常に参考になったのが、この和辻哲郎の『風土』だったのである。
本書は、和辻が1927年に最初にドイツへ留学したときのみずみずしい印象をもとにして執筆され、1935年に岩波書店から出版された。
「風土」とは和辻によると「ある土地の気候、気象、地質、地味、地形、景観などの総称」で、自然科学的な「自然」とは違う。地球上で人間が共同体的に生 き、他人との間柄を経験している環境は、地域によっていくつかの類型に分けられる。和辻は自分が実際に体験した三つの大きな風土の類型を区別した。中国や 日本を含む東アジアの沿岸一体の「モンスーン」型の風土、アラビア、アフリカ、蒙古などの「沙漠」型の風土、そして地中海から南ヨーロッパ、さらには西欧全体を含む「牧場」型の風土である。
モンスーン型の風土では湿潤が自然の恵みを意味し、自然は生の充満する場所となる。人間は自然に対しても他人たちに対しても受容的となり、独立した「個」の意識は成立しにくい。
沙漠型の風土は乾燥の世界で、人間は生を自然から闘いとらねばならぬ。ユダヤ教、キリスト教、イスラムなどの一神教は、沙漠型風土から生まれた。
牧場型の風土では、自然は人間に対して従順であり、人間は自然を支配して自然科学を発達させた。
罪の意識のような宗教的な観念の持ち方も、これらの風土の類型を基盤において考えると、単なる教義の違いよりずっと生命的現実に近いものとして、だから鬱病のような生きかたの病に際して意識に上りやすいものとして、その地域的な違いが理解しやすくなるように思われる。人間が「人と人とのあいだ」で感じとる 「自分のありかた」は、そういった風土に長年培養されて育ってきたものなのだろう。
2014年度
『省察』
デカルト
(三木清訳) 岩波文庫
(山田弘明訳) ちくま学芸文庫  西洋の哲学史を通じて屈指の名著である。もしこの本がなければ、哲学史は現在とは別のものになっていたかもしれない。
西洋の哲学史を通じて屈指の名著である。もしこの本がなければ、哲学史は現在とは別のものになっていたかもしれない。
最近、必要があって再読した。山田訳のちくま学芸文庫版である。この本を最初に読んだのは医学部の学生時代だっただろうか。当時入手できた三木清訳の岩波 文庫版だった。三木はこの『省察』を、太平洋戦争で軍に徴用されてマニラへ赴いていた時期に訳したらしい。その訳稿は、敗戦直後に彼が獄中で非業の死を遂 げた後に発見された。『構想力の論理』をはじめ他にも多くの仕事をかかえていた三木が、それでもこの「省察』を訳し終えたというのは、デカルトに対する彼 の深い思い入れを物語っている。
この本は、自分が存在するということを確かなこととして確認するために書かれた。「われ思う、故にわれあり」(コギト・エルゴ・スム)は、デカルトが自己 存在を確証するために用いた名文句だが、この「故に」(エルゴ)はこの本には出てこない。「われ思う」と「われあり」が理屈なしに直結している。「われあり」は、彼がすべてを疑いうるかぎり疑う「懐疑」の試みの結論として出てきた確信だった。
ところで、翻訳書を読むときにぜひ気をつけなくてはいけないことがある。それは原文の言葉(この場合はラテン語)と、訳文の日本語との、一語ごとの「守備 範囲」の違いである。ここではそれを「われ思う」について見てみたい。「思う」とは心に描くことだから、「考える」と同義とも受け取れる。事実これを英語 に訳せばIthink となって、これは「私が思う」と訳しても「私が考える」と訳してもいい。ところが日本語では少し様子が違う。日本語の「考える」のほうは知的な思考作業で ある。これに対して日本語の「思う」は、知的というよりもっと情緒的な色彩が濃い。「夢想する」というような心の動きは、「思う」とはいえても「考える」 とはいいにくい。
『省察』の「第二省察」にこんな文章が書かれている。手許の山田訳で引用すると「明らかに私はいま光を見、喧騒を聞き、熱を感じているが、私は眠っている のだから、これらは虚偽である。しかし見ている、聞いている、熱くなっているとたしかに思っていること、このこと自体は虚偽ではありえない。これこそ本来、私において感覚すると呼ばれていることである。そしてこのように厳密な意味では、これは考えることにほかならない」(50/51頁)。三木訳では「いま私はあきらかに、光を見、噪音を聴き、熱を感じる。これらは偽である、私は眠ってゐるのだから、といはれるでもあらう。しかし私は見、聴き、暖かくなる と私には思はれるといふことは確実である。これは偽であり得ない。これが本来、私において感覚すると稱せられることなのである。そしてこれは、かやうに厳 密な意味において、思惟すること以外の何物でもないのである」(44頁).
私が今回『省察』を再読して確認したかったことは、デカルトの言おうとする「コギト」が知的な作業としての「私は考える」や「思惟」でなく、もっと感覚的で受動的な「私に思われる」の意味であることだった。この点では三木訳も山田訳も落第と言わねばならない。心の動きを知性を中心にして捉える西洋語と、情緒を中心として捉える日本語との違いが明らかになったのは、予想外の副産物だった。
2015年度
『西田幾多郎』〈絶対無〉とは何か
永井均 著
NHK出版  これまでの『わたしが選んだこの一冊』で、私は西田幾多郎(『善の研究』)、和辻哲郎(『風土』)、デカルト(『省察』)といった古典の名著を取り上げてきた。今回は大転換で、私より20歳も若い気鋭の哲学者永井均氏の著書について書く。主題は西田幾多郎だから、この点では連続性がある。永井氏は河合文化教育研究所が毎年開いている「河合臨床哲学シンポジウム」にも出演していただいたことがあるから、私も面識がある。そのときの発表は「自己という概念に含まれている矛盾」についてで、これは『「自己」と「他者」』(木村敏・野家啓一編、河合文化教育研究所2013)に掲載されている。
これまでの『わたしが選んだこの一冊』で、私は西田幾多郎(『善の研究』)、和辻哲郎(『風土』)、デカルト(『省察』)といった古典の名著を取り上げてきた。今回は大転換で、私より20歳も若い気鋭の哲学者永井均氏の著書について書く。主題は西田幾多郎だから、この点では連続性がある。永井氏は河合文化教育研究所が毎年開いている「河合臨床哲学シンポジウム」にも出演していただいたことがあるから、私も面識がある。そのときの発表は「自己という概念に含まれている矛盾」についてで、これは『「自己」と「他者」』(木村敏・野家啓一編、河合文化教育研究所2013)に掲載されている。
永井氏の一貫したテーマは「私」とはなにかという問題である。われわれは誰でも自分のことを「私」だと思っているし、自分を指す一人称の代名詞として、ふつうに「私」を用いている。「ふつうに」といっても、われわれ日本人の日常会話では一人称や二人称の代名詞は「省略」されることが圧倒的に多いし、使われても相手次第で「ぼく」「おれ」「自分」等々、さまざまな語で代置される。しかしたいていのひとは「私」がなにを意味しているかを漠然と理解していて、必要さえあれば口に出して言う「用意」はできている。しかしそれはなにを言う用意なのだろう。なにかを言うたびに「アイ」や「ミー」を口に出す西洋人と違っ て、日本語に見られるこの代名詞感覚の不分明さは、永井氏の「私」論の、少なくともひとつの大きな要因になっているだろう。
永井氏はこの西田幾多郎論で、まず『善の研究』における「純粋経験」を検討し、それからこれを、われわれも昨年紹介したデカルトの「われ思う、ゆえに、われあり」の命題とつきあわせる。この命題には二つの二義性がある。第一に、これは西田にとっては「直接経験される事実」であるからそもそも疑ってかかる必要がない。これは端的に「思う、ゆえに、思いあり」以外のなにものでもない。第二に、この命題はデカルトによれば「私がこれを言い表すたびごとに[……] 必然的に真である」。となるとこれは論理的な真理である。西田はこれを拒否して、直接に経験される「生<なま>の事実」を求めた。
その後の西洋哲学史は、この「生<なま>の事実」ではない側を自立させる方向へと展開した。その頂点に位置するのがウィトゲンシュタインで、彼は「直接経験の事 実」(E)を「言語ゲーム」に乗せた。デカルトを「過失犯」とすればウィトゲンシュタインは、「確信犯」である。そして西田幾多郎は、それとは逆の意味でのもう一人の確信犯で、純粋経験が言葉と独立にそれだけで意味をもちうると考える。
この永井氏の西田論は、私のようにけっこう西田を読み込んでいるはずの人間にとっても三読四読に価する名著だと思われた。永井氏自身は「幸か不幸か、本書は、西田幾多郎の哲学の、わかりやすい解説書でもある」と書いているのだが。
2020年度
『ゲシュタルトクライス』知覚と運動の人間学
ヴィクトーア・フォン・ヴァイツゼカー 著 木村敏・濱中淑彦 訳
みすず書房
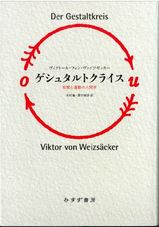 「生命あるものを研究するには、生命と関わりあわねばならぬ」(『ゲシュタルトクライス』)。
「生命あるものを研究するには、生命と関わりあわねばならぬ」(『ゲシュタルトクライス』)。
私が、学生時代の読書会で出会って以来、現在に至るまで圧倒的な感銘を受けてきた本に、ドイツの神経生理学者であるヴィクトーア・フオン・ヴァイツゼカーの『ゲシュタルトクライス』がある。
私はこの本によって、一人の精神科医として患者を自分の外にいる単なる治療の対象として診るのではなく、患者と私が同じ一続きの生命の中に生かされており、その生命の基盤をもとに、こうして生かされている私自身が同じように生きている患者を診る、ということの意味について考えさせられるようになった。
「生きる」という営みには、死を回避して生き続けようとする目的意志、あるいは生を是とし死を拒否するという価値観が不可避に含まれる。生きるためには、生きものは知覚と運動の両方を動員して環境との接触を可能な限り保持せねばならない。このようにして保持される環境との結合を、ヴァイツゼカーは相即Kohäxenz(コヘレンツ)と呼ぶ。環境との接触を失えば、生命体はすぐさま死滅するのである。
『ゲシュタルトクライス』の一番のキーポイントは、その生命体と環境との刻々に変化する関係の中で、環境の変化に応じてその相即を成立させるものこそが「主体」Subjektだと考えたことにある。つまり主体とは、それまで考えられてきたように個々の個体の内奥にある核のようなものではなく、むしろ個体と環境との接触面に出ているもののことであり、変化する環境に対応しながら、その接触面で生存を実現させていくもののことなのである。したがって、主体とは人間だけにあるのではなく、アメーバのような単細胞生物まで含むあらゆる有機体がもつものとなる。
私にとって、ヴァイツゼカーのこの思想が画期的に思えたのは、主体というものを個体の内部から取り出し、外へ、つまり環境との接触面へと移しただけでなく、主体とは、人間だけでなく単細胞生物まで含めたあらゆる有機体にあるものだとして、あらゆる有機体は、自ら生きるために環境の変化を知覚し判断し行動し、それによって主体的に環境との相即を保持すると看破したことにある。
ありていに言ってしまえぼ、彼は、近代の人間中心的な、つまり私という主体が外部の客体を認識するというような素朴な主客図式を覆してしまい、主体というものを環境との接触面に出しただけでなく、すべての有機体が主体を持っているとして、主体を心的、心理的なものから解放したのである。生きものの主体性とは、人間をも含めたすべての生き物が、「生きる」という根源的営みに参加し、「もの」としては認識できないこの生きるという「こと」の根拠に関わることである。この生きるという「こと」は、個々の生き物の有限の生命を裏打ちする大いなる生命のことでもある。「生それ自身は死なない。死ぬのは個々の生物だけである」(『ゲシュタルトクライス』)と彼が語るのは、この事態をさしている。
この本は、近代自然科学が徹底的に排除しようとした主体を医学に導入したばかりでなく、臨床医としての治療実践の中で、患者の主体性を重視し、患者が生きていることを医学の根本に置こうとした革新的な試みだといえる。
患者との臨床場面での経験から、人と人の「あいだ」というものを考え、個別の生きものと大いなる生命の問の「生命論的差異」について考えてきた私のこれまでの仕事は、この本なくしては成立しなかったといっても過言ではない。